鉄道唱歌 奥州・磐城編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!
平泉の観光・歴史などを、楽しく解説してゆきます!
↓まずは原文から!
戰ひありし衣川
金色堂を見る人は
こゝにておりよ平泉
さらに読みやすく!
戦いありし 衣川
金色堂を 見る人は
ここにておりよ 平泉
さあ、歌ってみよう!
♪たたかいありしー ころもがわー
♪こんじきどーうを みるひとはー
♪ここにておりよー ひらいずみー
福島駅→伊達駅(旧・長岡駅)→越河駅→白石駅→岩沼駅→仙台駅→岩切駅→国府多賀城駅→塩釜駅→松島駅→鹿島台駅→小牛田駅→石越駅→花泉駅→一ノ関駅→平泉駅→盛岡駅
※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋
一ノ関駅を出て、平泉駅へ
一ノ関駅を過ぎると、かつて平安時代にあの京都を凌ぐほどのピカピカの栄華を誇った、平泉の最寄駅である
- 平泉駅(岩手県西磐井郡平泉町)
に到着します。
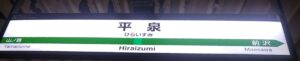
平泉駅(岩手県西磐井郡平泉町)
かつて黄金の栄華を誇った、宗教都市・平泉
平泉は、平安時代の1080年頃~1180年頃にかけて約100年間、あの京都を凌ぐほどの巨大な宗教都市(仏教を中心とした都市)として繁栄しました。
それは仏教・浄土による理想国家のようなもので、多くの素晴らしい寺院が建てられていました。
奥州藤原氏の栄華を物語る、中尊寺金色堂
中尊寺金色堂は、その時の栄華をわずかに伝える数少ない寺院です。
この100年間、平泉をはじめとする東北地方は
- 奥州藤原氏
という氏族の主導によって栄えました。
平泉が栄えた理由
その繁栄は、
- 馬など、東北地方の冷涼な地域ならではの産物を、次々に京都へ売り膨大な利益を上げたこと
- 京都とも下手に争わずに、良好な関係を築き続けていたこと
から、繁栄を保てていたともいえます。
奥州藤原氏の存在は、源頼朝にとって脅威に
しかし、1180年代になり源頼朝が鎌倉幕府を開こうとすると、東北地方で膨大な財力を持つ奥州藤原氏の存在は脅威となりました。
そして、1189年に平泉は攻め滅ぼされ戦火に包まれてしまいました。
そして、その後の歴史でも災害や戦禍などで街の寺院はことごとく焼失し、金色堂などをわずかに残すのみとなりました。
江戸時代に平泉を訪れた松尾芭蕉
江戸時代に松尾芭蕉が平泉を訪れたときは、
と世の中の無常さをしみじみと感じとられたようです。
平泉の歴史を、さらに詳しく これを知れば東北地方の旅が面白くなる
そんな平泉の歴史について、もう少し深掘りしましょう。
平泉の歴史をしっかり理解しておくことで、平泉の旅行や観光もより充実したものになります。
まず最初に、以下の重要キーワードを紹介します。
あとでゆっくり解説するので、すぐに理解できなくても問題ありません。
前九年の役とは?
「前九年の役」
1050年~1060年頃、源頼義が、現在の岩手県で安倍氏を滅ぼした戦い。
源頼義の息子・源義家も少し手伝う。
一度は安倍貞任に惨敗し、戦いは長期戦となったが、秋田の超有力氏族だった清原氏を味方につけ、形勢逆転。
安倍貞任の敗北・戦死により終了、安倍氏は滅亡した。
衣川でも戦った。
後三年の役とは?
「後三年の役」
1080年代に、息子の源義家(通称:八幡太郎)が、
- 現在の秋田県横手市で、
- 清原氏の身内同士の争いに介入し、
- (義家と)敵対する側の清原氏は滅ぼされ、
- 奥州藤原氏を誕生させた
という戦い。
しかし源義家は朝廷の命令で戦ったわけでなく、あくまで個人的に戦果を挙げたかっただけの戦いと見なされたため、報酬はもらえなかった。
安倍氏とは?
「安倍氏」
1050年頃の東北地方で力を付け始め、徐々に朝廷(京都)に従わなくなり朝廷の脅威となった氏族。
一度は岩手県一関市の戦いで、寒さを味方につけ源頼義の軍をボロボロに撃退し、これを機に安倍貞任のときに東北地方で完全にやりたい放題となる。
しかし、前九年の役で源頼義・源義家の親子と、秋田の清原氏によって滅ぼされる。
清原氏とは?
「清原氏」
出羽国(現在の秋田県、山形県)で、当時強大な力を持っていた氏族。
前九年の役で安倍氏に苦戦し、どうにもならなくなっていた源頼義は清原氏に目をつけて説得を繰り返し、様々な贈り物など巧みな交渉術で清原氏を味方につけることに成功。
結果、安倍氏を滅ぼし、前九年の役は終了。
後三年の役では、清原氏の身内同士で戦いが起こり、源義家が味方についた側が秋田県横手市の戦いで勝利、奥州藤原氏となる。
源頼義とは?
「源頼義」
前九年の役全般にわたり活躍・苦戦・奮闘した、朝廷の期待を一身に受け東北地方に派遣された陸奥守。
しかし、いざ戦いが始まると、仲間の裏切りや、東北地方の寒さ・地形などに翻弄され苦戦、多賀城まで撤退するなど、戦いはドロ沼の長期化を余儀なくされる。
そこで、秋田の清原氏をうまく味方につけ、安倍貞任を敗北に追い込み勝利。
息子に源義家がいる。
源義家とは?
「源義家」
源頼義の息子。
通称、「八幡太郎」。
前九年の役では父親のサポートで、命からがら負けたところを救ったりした。
父親の死後の1180年代、清原氏の身内争いに介入して、
- 「(義家にとって)味方の清原氏」と
- 「(義家にとって)敵の清原氏」
を争わせ、「後三年の役」が起こる。
そして秋田県横手市で敵対する側の清原氏を籠城で倒し、味方をした清原氏は奥州藤原氏となり、その後源頼朝によって滅ぼされるまで約100年の栄華を築くことになる。
源義経とは?
「源義経」
鎌倉幕府を開いた源頼朝の弟。
通称、「九郎判官」。
源平合戦のときは兄とは味方同士であり、兵庫県の「一ノ谷の戦い」など平家を西へ敗走させるなど、大きな戦果を挙げる。
しかし、鎌倉幕府の成立にあたっては政治に疎かったせいか、源頼朝と意見が合わなくなり対立。
東北地方へ逃れ、かつて自分を養育してくれた奥州藤原氏を頼る。
しかし、源頼朝が平泉を攻撃・奥州藤原氏を滅ぼし、源義経も悲劇の最期となる。
坂上田村麻呂とアテルイの戦いから始まった、東北地方の歴史
前置きが長くなりましたが、さらに深掘りしていきましょう。
平安時代の800年代~900年代は、東北地方では朝廷(京都)に従わない人達である蝦夷と、朝廷との間で争いが続けられてきました。
これまで何度も説明してきた
- 坂上田村麻呂
いう人物が、この時期に朝廷から派遣された武士の一人です。
また、彼と戦った蝦夷の代表的人物が、アテルイ(阿弖流為)になります。
朝廷に従い、仲良くした「俘囚(ふしゅう)」
そして平安時代1050年頃の東北地方は、無駄に京都と争わないよう、ある程度の均衡(仲良し)が保たれていました。
こうした、朝廷に従順な東北地方の人々を、当時は「俘囚」といいます。
朝廷から東北地方の監視や平定のために使わされた武士のことを、「陸奥守」といいます。
この、陸奥守と俘囚の関係は良好だったといえます。
安倍氏の「やりたい放題」が始まる 朝廷に税金も納めない・・・
その俘囚の中から力をつけ、影響力を持ち始めたのが、安倍氏でした。
安倍氏は、1050年頃、東北地方でまさに「やりたい放題」やっていました。
朝廷に従わない、税金も納めない・・・。
これではイカンということで、朝廷は源頼義に安倍氏追討を命じます。
ここに、1051年から約11年にも及ぶ、前九年の役が始まります。
「前九年の役」朝廷による安倍氏討伐命令 しかし寒い東北地方で苦戦
前九年の役は、
- 裏切り行為
- 東北地方という寒冷地で慣れない戦いを強いられたこと
などにより、朝廷側は苦戦を余儀なくされます。
現在の岩手県一関市でお起きた安倍氏との戦い(黄海の戦い)では、兵士数百人が死亡するという大敗に追い込まれてしまいました。
源頼義は、息子の源義家に支えられ、命からがら安倍氏から逃げ、多賀城に引き返します。
これをきっかけに、安倍貞任が支配する東北地方は、もはややりたい放題。
税金も払うはずなく、(朝廷側に本来は治められるはずの税)も全部せしめる(自分のものにする)という、やりたい放題ぶりでした。
長引く「前九年の役」 そこで秋田の清原氏に助けを求める
さすがにこれは見過ごせない、ということで朝廷側は、
- 出羽国(現在の秋田県・山形県)
で強大な権力を持っていた清原氏に多大なおもてなしを続けたのでした。
その結果、清原氏を味方につけることに成功します。
安倍貞任の戦死 「前九年の役」の終わり
清原氏の大軍を味方につけた朝廷側・源頼義の軍は安倍氏を滅ぼし、安倍貞任は戦死しました。
前九年の役はズルズルと約10年ほど長引いたものの、結局は朝廷・源頼義・源義家、そして秋田の清原氏の勝利に終わり、安倍氏が滅亡する結果となりました。
「後三年の役」が始まる 秋田・清原氏の内輪揉めに始まる争い
しかし、その後に「後三年の役」という約3年間におよぶ戦いが始まります。
源頼義が1070年代に死去し、息子の源義家の時代となってからのことです。
当時秋田の清原氏では、身内同士の争いが起きていました。
つまり「清原氏A」と「清原氏B」にわかれ、身内同士で戦うイメージです。
ここで源義家が清原氏Aに味方をして身内争いに介入してきます。
なぜ源義家が介入しがったのかというと、意図的に戦いを引き起こし、手柄を得て朝廷から報酬を得たかったからとも言われており、陰謀もあったとされています(諸説あり)。
「後三年の役」の終了 そして奥州藤原氏の誕生
敵に回された清原氏Bは、秋田県横手市にて籠城します。
しかし、城にあった備蓄・食糧はあっという間に食べ尽されてしまい、清原氏Aと源義家に敗北しまいます。
ここに後三年の役は終了となります。
勝った清原氏Aは、先祖の「藤原」に苗字を変えたため、これが奥州藤原氏の始まりとなります。
奥州藤原氏は、その後100年間の栄華を築くことになります。
しかし、一方の源義家は朝廷から命じられたわけではなく、ある意味勝手に戦ったため、結局目的だった報酬は得られず、その後朝廷から不遇な扱いをされたとされます。
奥州藤原氏の時代へ 平泉を拠点とした100年の栄華を築く
その後は奥州藤原氏の時代となります。
奥州藤原氏は、1080年頃から1180年頃まで、約100年にわたって東北地方に栄華を極めます。
過去の幾度の争いから「戦のない世の中を作ろう」ということで、仏教や浄土をモチーフとした、寺院であふれる理想的な世界を平泉に作りあげたのです。
源頼朝により平泉は滅ぼされ、奥州藤原氏は滅亡へ
しかしその栄華もつかぬ間、100年後の鎌倉時代になる際に、新しく鎌倉幕府を作ろうとしていた源頼朝にとっては、東北地方で強大な奥州藤原氏は脅威となり、敵とされてしまいます。
最初は鎌倉との衝突を避けるために、ある程度は奥州藤原氏も融和的に同調します。
しかし、結局は戦いは避けられず、鎌倉軍は平泉に侵攻、奥州藤原氏は滅亡します。
当時の栄華をはかなく今に伝える、金色堂と平泉
そしてその後の世の中においても、平泉の寺院や華々しい街並みは戦争や火災などで焼失していき、やがて金色堂などの豪華な建物をわずかに残すのみとなりました。
金色堂は、当時の平泉の栄光を、現在もはかなく今に伝え続けています。
松尾芭蕉も、江戸時代になって平泉を訪れたときに「どんな栄華も、それはいつまでも続かないんだなあ」と世の中の無常を悟ったとされています。
頼朝に追われたもう一人の悲劇のヒーロー・源義経
また、源頼朝と一緒に平家を打倒した人物として、源義経がいます。
平泉は、源義経最期の地としても知られています。
彼は「九郎判官」の異名をもち、鎌倉時代に入る前の源平合戦において兵庫県で行われた「一ノ谷の戦い」で、既に劣勢に追い込まれていた平氏と戦い、勝利しました。
敗北した平氏はさらに西へ逃げ延びて、山口県下関市の壇ノ浦で完全に滅ぼされてました。
これによって平氏は滅亡、源氏の勝利となり鎌倉時代が始まるわけです。
源東北地方(平泉)へ落ち延びた義経 そして衣川館での悲劇の自害
この通り、源義経は源平合戦で手柄を挙げた功労者であるはずなのに、鎌倉幕府が開かれると政治のやり方や考え方で源頼朝と対立します。
義経は戦いをやらせれば天下一だったが、政治に関しては向いてなかったとされています。
源頼朝も、「もう義経に用はない」と言わんばかりに、義経を殺せと命令します。
この時代には、かつての味方は今の敵、ということは普通にありました。
身内同士なのに、協力するどころかむしろ争うというのも当たり前の時代でした。
平泉の奥州藤原氏を頼る
これによって義経は、東北地方に逃げ延びることになります。
そしてたどり着いた場所が、平泉というわけです。
平泉には、かつて幼少期に自分を養育してくれた奥州藤原氏がいました。
源頼朝は、義経を逃がさないために、あちこちに関所を設けて取締りさせました。
義経がどのようなルートを通って平泉に着いたのかは諸説ありますが、日本海側の
- 安宅の関(石川県小松市にあった関所)
- 鼠ヶ関(新潟県と山形県の県境にある関所)
をくぐり抜けたとも言われています。
また、どうやって関所をくぐり抜けたのかも謎です。
裏切りにあい、悲劇の自害へ
ともあれ、命からがら平泉にたどり着いた義経でしたが、結局はかくまってもらった奥州藤原氏の人物が死去してしまいます。
すると、代わりに引き継いだ息子が鎌倉軍に屈してしまって裏切ってしまい、裏切られた義経は悲劇にも殺されてしまいました。
1189年のことで、いわゆる「衣川の戦い」の出来事です。
そして、義経の部下だった弁慶という人も殺されました。
あの「弁慶の立ち往生」で有名ですね。
立ったまま死んだわけです。
判官贔屓(ほうがんびいき)
また、源義経は奥州まで逃げてきて、裏切られて自害に追い込まれた悲劇の人物であることから、同情を誘うという意味で
- 判官贔屓(ほうがんびいき/はんがんびいき)
という言葉もあります。
「判官贔屓」という言葉は、不遇な立場に追い込まれた弱い人を同情する、という意味に転じて使われます。
判官贔屓については、さらに以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。


衣川(東北本線・平泉駅~前沢駅間)(岩手県)
平泉の観光・歴史をしのびながら
平泉は、東北地方の戦いや栄華の歴史を、今でも現在に伝え続けています。
今回は説明が大変長くなりましたが、東北地方の戦いの歴史や平泉の栄華など、少しでも理解していただけたなら幸いです。

平泉駅(岩手県西磐井郡平泉町)
現在の平泉町の景観も、とても風情があり歴史ある街並みの様相を成しています。
平泉駅の駅舎は、2011年の東日本大震災のときにかなりダメージがいったそうですが、その後大きくアップグレードされ、現在はとてもピカピカで豪華です!(「東北の駅百選」に選出。)
平泉を出たら、次は盛岡方面へ
平泉観光が終わったら、再び列車に乗り込み、
- 奥州市
- 北上市
- 花巻市
そして、盛岡市を目指して進んでいきましょう!

コメント